相対音感保持者のわたし。
絶対音感ありません(>人<;)
すると、あらゆる調で、
「その調の」ドレミファソラシドでメロディが聞こえます。
これっていわゆるクラシック的な「楽譜を見て演奏する」ということと、
相性が悪いというか、なじまないのですね。
今日はその辺について軽く書きます。
耳コピピアニストはこうして誕生する
耳コピピアニスト、というのは、
こんな感じでピアノに取り組んでいることが多いかと思います。
基本的には、
「曲を覚えるフェーズ」
「ピアノを練習するフェーズ」
っていう二つのフェーズがあるんです。
「曲を覚えるフェーズ」
(1)西野カナさんが休養宣言をしたというニュースを見て、
そういえば聞いたことなかったなあ、と思って、YOUTUBEなんかで聞いてみる。

(2)西野カナの曲では「Darling」という曲が、自分は好きだなあ、などと興味をもつ。「Darling」という曲をスマホで鬼リピートするようになる。
(3)何回も聞くうちに、歌詞と一緒にメロディも覚えてしまう。
メロディを歌えるようになった時点で、楽譜化する準備は整った。
(4)IwriteMusicのような、楽譜を書けるアプリを使って、楽譜を書く。
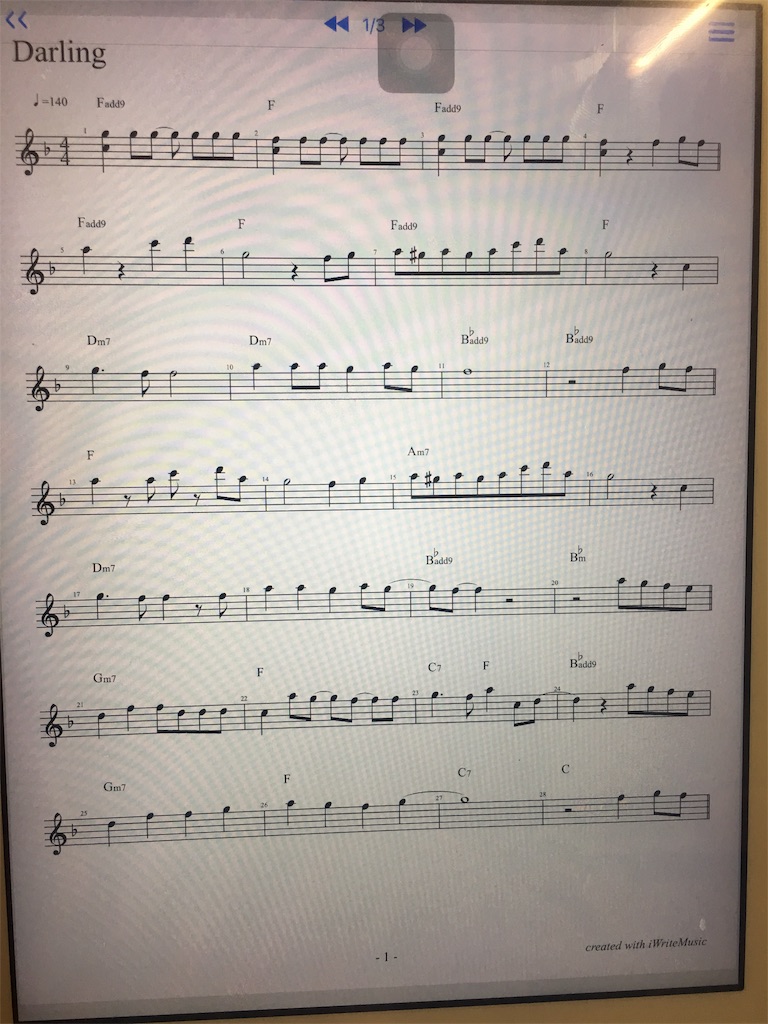
↑私が採譜した西野カナの「Darling」
これは普通の人には驚愕する能力かもしれないけど、
歌を正しく歌える人だったら、相対音感は基本的にあるはずなので、
「単なる慣れの問題」だったりします。
自分が歌ってる音の高さと、音符の音の高さが一致すれば正しいので、
それを書けばよい。
なれると、相対音感が育って、メロディがドレミで聞こえる確率がアップします。
スラスラと書けるようになります。
しかし、音の長さとか、休符、とかをちゃんと書けないとできない。
これを「リズミックノーテーション」と言い、
基本的な楽譜の書き方を学べばわかります。
↑これは、その辺の事情を扱った良書。決定版的な一冊ですね…
(5)私はコードは聞き取りが困難なので、ネットで調べてます。
実際に弾き歌いをする。
コードと歌が合ってなかったら、「あれ?なんか違うかも」と気づくものです。
(6)メロディとコードを記述したら、楽譜が完成!
以上です。
耳コピにピアノは全然使いません。
使うのは、耳と自分の声だけです。
ミュージシャンとは、そうあるべきかな、と勝手に思ってます。
道具はiPhoneとiPadを使うので、家にいる必要もありません。
電車やバスに乗ってる暇な時間にやってます。
1曲の採譜に、2-3日かけてます。
「アプリの使い方」
「リズミックノーテーション」
「歌唱力(歌はうまくなくていいが、音程が正確)」
「相対音感」
ここまでが曲を覚えるフェーズ。
なんとなく、クラシックピアノやってるのに、歌わせると音痴だなあ、という人がいるものですが、そういう人は、上にあげたような能力が鍛えられていないためだと思います。
耳コピピアニスト特有の難しさ
で、いよいよ次に、実際にピアノの前で
「ピアノを練習するフェーズ」に入ることになるのですが、
メロディとコードを記載しただけの楽譜を使って、
それを適当にアレンジしてピアノを弾くことになります。
これが、なかなかノウハウがいるところです。
音楽理論とか、アレンジテクニックが必要なのです。
クラシックピアノでは、あまり求められない能力ではないでしょうか。
難しさその1
相対音感保持者の場合、頭の中のメロディはその調のドレミファソラシドで鳴っている。
西野カナの「Darling」の歌いだし歌詞で言うと「ねえダーリン、ねえダーリン」のところを例にとると
キーがFで
ファーソファラー、ドーレーラー、と弾くべきですが、
頭の中では
ドーレドミー、ソーラーレー、のような音が鳴っている。
だから、実際弾く音を、瞬間移調して弾いているのですね!
「そんなこと出来るのか!」と思うかもしれませんが、
相対音感の耳コピピアニストはみんなやってるんじゃないかなあ。
こんな感じなので、耳コピピアニストは
楽譜を弾くのが苦手な人が多いと思います。
難しさその2
クラシックだと、右手パートはこう、左手パートはこう、と
「ちゃんとした楽譜」があるものです。
しかし、耳コピピアニストには、まともな楽譜は存在しません。
コードネームや曲のリズムパターンなどから、こうやって弾こう、と
独自のアレンジを繰り出していかないといかんのです。
ここが難しく、かつ独創性を求められる楽しめるところでもあると思います。
お読みいただきましてありがとうございます。
